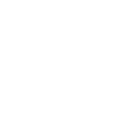.png)
.png)
長谷川 靖哉
人類の進化を照らす希土類発光体
北海道大学大学院工学研究院
物質化学部門
先端材料化学研究室
.png)
人類の進化を照らす希土類発光体
2014年春、北大拠点の次世代発光体プロジェクト始動。
世界一タフな「カメレオン発光体」も次のステージへ。
当研究室の研究素材である希土類(レアアース)とは、希少金属(レアメタル)に属する元素群の一種です。我々は希土類が持つ“美しい発光を示す”特性に着目し、希土類を使った新発光体の合成に取り組んでいます。一般に発光体の合成には有機色素分子や半導体が使われていますが、我々の最大の特徴は、希土類に有機分子を取りつけて希土類錯体を作るというまったく新しいアプローチを試みているところにあります。
高効率で光る=強く光るには、光エネルギーを蓄える力が非常に重要です。たっぷりと光エネルギーをチャージする力とアウトプットする力。この二つの相乗効果で強く光ることが可能になります。我々が希土類に取りつけた有機分子は光をチャージする力が非常に高いため、“より強く、より美しく光る発光体”の合成を実現することができました。
こうした学術研究の成果を実社会の産業化に展開したいと考えたとき、最大の壁は耐久性です。ほとんどの分子は150〜200℃前後で燃えてしまうため、耐熱性に難があります。そこで、我々は「なぜ分子は燃えるのか?」という根本を見つめ直し、分子の構造を考えるところから始めました。高温下にある分子は分子同士が回転や伸縮を繰り返し、結合がほどけた部分から酸化が進んで燃焼します。ならば、いかにして結合が崩れない強固な構造の分子、高温でも燃えない分子を作るか。その設計が試行錯誤の連続です。
2013年に発表した「カメレオン発光体」は、熱に強いタフな発光体を作り上げていく過程で誕生したものです。希土類のユーロピウム(Eu)とテルビウム(Tb)を組み合わせた発光体で、低温では緑色、室温では黄色、高温では赤色に発光することから「カメレオン」という名称を付けました。
「カメレオン発光体」は塗料にもなるので、物体の表面に塗布し、その色の変化から表面温度を正確に計測することも可能になりました。しかも250℃からマイナス100℃というかつてないほどの広範囲で温度を測定することができるため、これに大きな関心を示したのが宇宙航空研究開発機構JAXAです。絶対零度の宇宙から超高温状態になる大気圏に突入する大気圏突入型宇宙船の設計には、表面温度の観察が非常に重要な役割を果たします。「カメレオン発光体」は発光反応が速いという利点もあり、秒単位で記録される発光変化の測定に最適と認められ、現在JAXAとの共同研究が進んでいます。
他にも超音速旅客機や化学プラント、高速鉄道、自動車のデザイン設計等、今後の応用範囲は皆さんのアイデア次第。この「カメレオン発光体」がきっかけとなって、「北大でこんなにすごい研究ができるなら、自分もいつか」と高校生たちの学ぶ意欲が盛り上がってくれたら、あるいは「この技術を使ったらもっと面白いことができそうだ」と思っていただけるような意欲的なものづくり企業との出会いにつながれば、と期待しています。
今後バージョンアップしていく「カメレオン発光体」を含め有機分子を組み合わせた希土類錯体は、大学院理学研究院化学部門錯体化学研究室の加藤昌子先生との共同研究の成果です。加藤先生は錯体合成のエキスパート。分子の機能は構造と直結しており、発光体の特性を高めるには分子構造を知ることが必要不可欠です。我々が分子を設計し、加藤先生がその分子構造を解析してくれる。理工連携のコラボレーションが世界最先端の研究につながると再認識できました。
北大は理学と工学が統合した全国初の化学専門大学院「総合科学院」の存在が示すように、理学部で行われている世界トップレベルの学術研究と、実学を追求する工学部の社会貢献の姿勢が実にバランス良く噛み合っています。このことは世界の最先端研究を生み出せる北海道大学の強力なアドバンテージであると強く確信しています。
2014年4月からは本学で私がリーダーを務める大型プロジェクト「次世代省エネを指向した強発光性の希土類錯体ポリマー開発ー新規エレメントカップリング反応を鍵とするフォトニック錯体工学拠点の形成ー」が始まります。北大を拠点に、地球環境にやさしくかつ省エネで高機能、耐久性が高い次世代発光体の研究開発を進めてまいります。また、学外においても企業コンソーシアムとの共同研究が始まる予定です。
人類の歴史は「光」の歴史です。狩猟生活を活発化した火に始まり、エジソンの電灯で夜が明るくなり、現在ではLEDが皆さんに身近なスマホに活用されています。これから開発される新・希土類発光体は人類を次の進化へと誘うもの。私たちの未来を大きく革新に導く可能性を持っています。